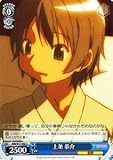
ヴァイスシュヴァルツ 【上条 恭介】【C】 MMW17-092-C 《魔法少女まどか☆マギカ》
- 出版社/メーカー: ブシロード
- メディア: おもちゃ&ホビー
- この商品を含むブログを見る
基本的に本エントリも、劇場版を既に見たことを前提にしておりますので、予めご了承下さい。
なお、本エントリは、フォロワーの@haka_lib様のアイディアから派生したものです。深くお礼申し上げます。
1.緑の子の怒りはどこへ向く?
志筑仁美は悩んでいた。思い続けた憧れのあの人、上条恭介とつき合うことになったのはいいものの、上条君は演奏会に向けバイオリンのレッスンで大忙し。デートの約束をしたくても断られっぱなしである。
どうせ会えないなら日曜などなくなってしまえばいい!!
これじゃあ、ナイトメアも登場するのもいたしかたない。
この精神的苦痛、どう癒してもらおうかしら!?
しかし、流石の仁美ちゃんでも、上条君に直接謝罪と賠償を求めるだけの図々しさはない。
そうだ!
上条君は事故で怪我をしている。つまり、事故の加害者に対し、損害賠償請求権を持っており、事故の加害者から賠償を取り立てることができる。もし、上条君が無資力なら*1、債権者代位権(民法423条)を行使して直接加害者から賠償金を取り立てることができるのだ。
とはいえ、重大な問題がある。それは、上条君が請求できる損害の大部分は後遺症を負ったことにより、将来バイオリニストとして期待される収入を失ったことによる損害である。
「奇跡も魔法もあるんだよっ!」で後遺障害が治癒した後は、その分は請求できないのではなかろうか。
2.法的な整理
民事裁判には、判断の基準時がある。つまり、判決をする以上、ある時点における事実関係を前提に判断をせざるを得ないということだ。この時点は、専門用語では、事実審口頭弁論終結時というのだが、概ね*2判決の直前だと考えてもらっていい。
すると、もし、加害者に対して訴訟を起こして判決が下された時点が、奇跡か魔法か何かで上条君が治癒した後だったら、基本的には後遺症はないとして判決がされる。
問題になるのは、後遺症が治る前に判決が下されて確定し、その後奇跡か魔法で後遺症が治癒した場合である。例えば、入院中に既に訴訟を始めていて、第一審で判決が下され、控訴もなく確定したといった場合が想定される。この請求権につき仁美ちゃんが加害者に対し支払いを求めた場合、大原則は、一度確定した判決は、もう覆せない*3というものとなるが、それでいいのだろうか?
この問題を法的に整理すると、こうなるだろう。
Yは交通事故でバイオリン奏者Xに怪我を負わせ、後遺症によって演奏不能な状態にした。XはYを訴え、逸失利益として1億円の支払いを命じる判決が確定した、奇跡か魔法か何かにより、Xはバイオリンが演奏できるレベルに回復した。Yはどのような法的手段が取れるか。
3.確定判決の持つ効力
判決が確定することで、裁判所や当事者は、すでに確定された終局判決に矛盾する判断や主張を行うことが許されない。この効力を既判力という(民事訴訟法115条)。
このような既判力が認められたのは、手続保障とそれにもとづく自己責任といわれる。つまり、裁判手続においては、両当事者とも、証拠や主張を十分に提供して争い、第一審判決で負けても控訴、第二審判決で負けても上告をして判決の変更を求めることができる。このような適正手続が保障されている以上、そのようなプロセスを経て下された判決の結果は、まさに当事者の「自己責任」なのであって、後からこの結論についてとやかく言うこと(蒸し返し)を認めるのは、むしろ当初の手続で努力して有利な結果を獲得した相手に対して不公平であろう*4。
このことが意味するのは、誤判であっても、確定判決にはとやかく言えないということである*5。例えば、お金の貸し借りで、お金を「返した」のか「返していない」のかが問題となった場合に、裁判所が「返していない」と判決したとしよう。でも、真実は返していたという場合だってある。そういう真実と異なる判決であっても、それが確定してしまえば、もはや誰も争えないのである。
この点、例えば、裁判官が賄賂をもらって相手に有利な判決を下したとか、証拠が偽造文書だったといった例外的な場合には、この原則を守るのは不当であろう。そこで、再審という制度があり、非常に限られた例外的な場合に、再審の訴えというルートを通じて、既判力の排除を求めることができる*6。もっとも、極めて例外的なルートであって、認められることは極めて稀である。
本件のような、確定判決が認定した後遺障害の程度が判決後に変わるというのは、魔法少女契約を締結した際の「願い」によって生じる場合もあるが、それ以外の理由によって生じる場合もある。このような場合について、確定判決に基づき払わなければならない額と、軽快によって損害が減った分の差額を不当利得として返還請求できるという見解もある*7。しかし、確定判決の時点で既に負傷という事実自体は発生しているのだから、裁判官による予後についての予測が外れただけという評価になるだろう。すると、まさに誤判があっても、再審事由がない限り確定判決の判断を後で争うことはできないという趣旨が本件でもあてはまるだろう。奇跡や魔法は再審事由ではないのだから、いくら客観的真実と合致していないといっても、既判力で確定した権利を争うことは許されないだろう*8。
ここで、毎月50万円づつの200回払いといった支払い方(定期金による賠償)であれば、判決確定後に『後遺障害の程度』等の事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができるとされている(民事訴訟法117条)。本件のような、一括で1億円の支払いを認めた事案についても、この条文を類推するという議論はあり得る*9が、今の所これを認めた裁判例はないようである。
4.最後に残った最高裁判例?
ところが、こういう事案に対し、画期的な解決をした最高裁判例があった。この事案は、荷馬車引き営業*10を行う「被害者」が、交通事故で負傷したため、「加害者」に対して損害賠償を請求し、一生家業の荷馬車引き営業をできなくなったことによる逸失利益を求めたところ、勝訴判決を得てこれが確定した。ところが、「被害者」は、早々と回復し、再度、荷馬車引き営業を開始していた。反面、加害者が損害賠償を苦に列車に飛び込み自殺をしていた。そのような状況で、「被害者」は、「加害者」の遺族の財産に対する強制執行をして、強制的にこれを取り立てようとした。これに対し、「加害者」の遺族が、異議(請求異議)を申し立てた事案である。
最高裁は、このような事案で執行を行うことは、それが如何に確定判決に基づく権利の行使であつても、誠実信義の原則に背反し、権利濫用の嫌いがあるとした。そもそも、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない(民法1条2項)。確定判決に基づく権利も、その行使は信義に従い誠実に行わなければならない。すると、確定判決自体は争えないとしても、このような状況で、確定判決に基づき執行をすることが、執行権の濫用に当たるとして、公平な解決を図った訳である。
この判例に対しては、執行手続自体には問題がない以上は無理な解釈だという批判もある*11が、このような事案について、既判力を認めながら落ち着きのいい解決を図るという意味で画期的と言えよう。
本件でも、緑の子が加害者に対し、確定判決に基づき執行をかけて来た場合には、加害者は、上条君の傷が治癒しており、もはや確定判決の前提となった後遺症がないことを理由に、「執行権の濫用」を主張して、執行を排除することができるだろう。
まとめ
「奇跡や魔法」による驚きの結果が生じた場合、一見、現在の法律や法理論で解決することはできないかのように見える。
しかし、最高裁は不当な結論に対しそんなの、あたしが許さないと、考えられる法理論を駆使して合理的な結論を導く。
そう、奇跡があっても、魔法があっても、法律は、それを熟知さえしていれば、妥当な結論を生み出してくれる、最高の友達なのだ。
ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシルの刑事訴訟法的検討〜多様性社会と適正手続 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常を
セキュリティホール memo様にご紹介頂きました。ありがとうございます。
*1:上条君は金持ちだからそんなことはないだろうというかもしれないが、よく考えてみると、お金持ちなのは上条君の両親であって、上条君が持っているのはあくまでも、莫大な遺産の「推定相続人」としての期待に過ぎないと思われる。
*2:最高裁まで行った場合は、高等裁判所の判決前に「口頭弁論を終結」という手続をとるので、この段階になる。
*3:簡単に覆されても困る
*5:「既判力は、前訴判決が仮に誤っているとしても後訴裁判所を拘束する」
*8:石川明「判批」法学研究36巻9号88頁
*10:なんか時代がかった感じですが、元々の損害賠償支払を命じる判決が言い渡されたのが昭和26年ですので…
*11:中田淳一「訴と判決の法理」203頁